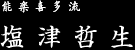Vol.03 「父」
父の遺産
父は子供の頃、祖父の師であった熊本の友枝三郎師に入門、修行していたという。初舞台は隅田川の子方。能の本格的な修行には東京へ行かねば、と十 四世喜多六平太(先々代宗家)の元へ入門、 大正末期から昭和の初期にかけ、内弟子として入り稽古を積んだ。宗家から能楽の普及のため朝鮮に行くよう命ぜられ、昭和十二年、京城で流儀拡張、門弟の指 導に力を注いでいたが、第二次世界大戦勃発、そして終戦。引き上げの際、荷物の重量制限で永年の能修行の財産である手附、型附等書附をとるか、産まれたば かりのわが子(小生)をとるかの選択をさせられ、断腸の思いで、こと細かに記した書附を捨てての帰国であった。愚痴、悔みなど一切云わぬ父で、子供の私に は一言も話さずじまいであった。
父は普段は誰にも愛想よく、ニコニコしていたが、稽古は厳しかった。子供の私に厳しくするのは解るが、お弟子(素人)の稽古にも容赦なかった。子供心に月謝を払って楽しみにいらしている方なのだから、そこまで叱らなくてもと思うほどであった。
稽古したくとも本が無い、という人がいると、謡の文章と節をわら半紙に書き、コヨリで綴じて謡本を作り、それを与えて稽古を始めたそうである。今も残る数冊の父手書きの謡本を手にして胸塞がる思いである。
ワープロだ、コピーだという時代、正に気が遠くなるような話である。熊本に引き上げてから後に記した伝書、今の私には虫めがねでなければ読めぬような細か な文字、筆で記した厚さ4~5センチの和綴じのものが十冊、二百曲に及ぶ。最後まで乱れぬ筆跡とその内容に父の能への執念がひしひしと感じられる。これは いったい誰のために記したのであろう、とページをめくるたびに思ってしまう。自分自身の記憶のためであろうか、もしかして跡を継いで欲しい私のためにであ ろうか、かけがえのない父の遺産である。
能への思い
父は何としても子供の私に能の道を継がせたかったらしい。
毎日食べていくことさえ困難な日々、お弟子の稽古さえ戦災を受けなっかた土地まで出かけなければならず、とても自分の稽古に明け暮れる余裕などなかったはずの時代にである。
生活の展望もまだ開けぬとき、父は、私を能の修行のため単身東京に送り出した。時に父六十四歳、私が十四歳中学三年の時であった。「東京にいくか?」とい われ、未だ見ぬ都会への憧れがボンヤリとあったくらいで将来のことや、能楽の道を歩もうという確固たる決心など及びもしなかった。豊かな生活が送れる、華 やかな社会で活躍出来るなどといった思いがなかったことだけははっきりしている。
父は自分の果たせぬ能への思いを私に繋ぎたかったのだろうか。こんなにも素晴らしいものがある、何としてもお前に舞わせてみたい……と。おそらく父の能 への執念が私をこの道へ放り投げたのであろう。能に対するすさまじい執念の持ち主であった父も、私達子供の面倒はよく見てくれた。何せ母がいないので、家 事も稽古の合間をぬってすべてやっていた、。七輪の火を起こし、なすびを焼き、フウフウと口をとがらして皮をむいていた姿や、練炭火鉢に黒豆を入れた鍋をかけ、時々かき回すようにといいつけて、下駄を突っかけ稽古に出かけていった面影が今も鮮やかに残っている。御馳走とまでいかないが、手の込んだ料理も 作ってくれた。ある日学校から帰ると、父は着物にたすきがけで、鰯をおろし、皮をむいていた。擂鉢ですり身にし、小麦粉を混ぜて団子を作り、油で揚げると美味しいぞ、という。擂鉢のふちをしっかり押さえていろ、という父の言葉で、必死で押さえてはいたものの、すりこ木を懸命に掻き回す父の姿に、何か胸が一 杯になり、とうとう泣き出してしまったこともあった。その時のいわし団子は世界一の味、いまも食べるたびに蘇る。
父の芸風・真の力
子供の頃から、いやでも耳に入っていた父の謡を、私は生意気にも少しも上手いと思わなかった。朗々と謡うというには程遠く、どちらかといえば悪声 に近く、調子も良いとは思えなかった。しかし大勢の中に入って謡っている時は何故か良く声が通っていて、回りの声をまとめて引っ張っていた。上手か下手か 確かな処は解らないままいなくなってしまったが、永く父に教えを受けたお弟子さん達の力の入った確かな謡を今聞くと、私の聞く耳がなかっただけで、父の謡 は実はいい謡であったのかもしれない。かたくなに録音をさせなかったので、いまでは聞くすべもない。
父の謡は正直なところ、解らずじまいであったが、舞姿は実に端正で美しかった。スイスイと千鳥が浮かぶかの如き足の運び、軽やかにそして鮮やかな 扇つかい、淡々と舞っているようでいて、居合の達人のようなスキのない力強さ。扇をそのまま刀に代えても、誰も打ち込めないのでは、と思わせる程の気合が 八方に充ち溢れた舞姿であった。出来あがった写真全て、どれも正しく立派で美しかった。
晩年父の「山姥」の仕舞をビデオに撮って観せた事があった。八十にして初めて動く自分の舞姿をくい入るように観ていた。感想を聞きたくてもとても聞ける雰 囲気ではなく、ただ黙って考え込んでいた。もしかしたら「自分は八十年の間、何をやっていたのだろう……」と愕然としていたのかもしれない。観る人の心を 打つ大きな要素は舞う姿・形を通して、舞手の心、気迫、すなわち眼にみえぬ内面のエネルギーに依る処が大きい。力の無い者はいくら暴れ回っても、観る人は 何も感じないし、真の力を得た人は、立っただけで動かずとも観る人の心を捉えることが出来る。能の能たる核はそこにある。映像は眼に見える形だけを映し出 し、心の動きはすべて断絶してしまう。能を映像によって解らせようなどの発想がナンセンスだったのである。初めて観た自身の映像に大層な衝撃をうけたであ ろう父に、何も云わなかったのが悔やまれる。
私が東京に出て、少し解りかけてきた頃、父の芸と私の行き方は全く違うのでは…と思っていた。気合を入れろ!肘を張れ!腰を引け!顎を引け!と怒 鳴られての毎日であった。私は、アンコウのように眼を吊り上げ、千里先まで気を通せとの思いで顔を真っ赤にして、柱も吹き飛ばす程の勢いで、一番舞えば汗 びっしょり、青息吐息であった。涼しい顔をして汗もかかず、軽やかに舞う父の芸とは全然別だと信じていたものである。ある時、父と同時代の大先輩が「お父 さんによく似てるな。でもお父さんはそんなもんではなかった。もっと激しく強かったよ。」と言われ、あらためて凄さを知った。
父が古稀(七十歳)、私が成人(二十歳)の時、家元から祝いにと、二人乱という大曲を許された。体力、気力バリバリのつもりの小生、師喜多実先生に「最低 百回の稽古をしなければ、」と言われ、自分なりに充分な稽古を積んで臨んだ。昭和四十年、熊本大洋デパートのホールであった。二人共ほぼ同じ背格好、同じ 面に同じ装束、どちらが親か子か解らぬ方も随分いらしたらしい。気負い過ぎからか、途中何度かよろけてしまった。終了後、ある人が「乱は大曲、七十のお歳 ではさすがにお辛かったのでしょう。一寸よろけられましたね」と言われた。「よろけたのは私ですよ。」と訂正すると、唖然としておられたそのお顔が懐かし く思い出される。
真の美を求めて
父は一生ぶきっちょで世渡りの下手な人であった。
すべてに無欲で、八十九歳の生涯を閉じるまで借家住まい、自分の家というものを持たなかった。晩年の二十五年間は藤崎宮の舞台で寝起きをしていた。舞台がなければ能は舞えん…という舞台への捨て難き執念からであろうか。好きな時に舞えて幸せだったのかも知れない。
今の時代、能は観客を相手に舞うことが大半であり、必然的に観せようとする意識が働いてくる。時代の流れと共に、演劇としての能の素晴らしさを観 せることは良いことには違いない。しかし能の本質から離れていく危険性をはらんでいるように思う。父の、能と共に歩んだ生きざま、その証としての舞台を、 この眼で確りと見てきたからである。
父の一年の舞台数はわづかに四、五番、それも相手は神様であった。神に媚びを売って何になろう。小細工をして格好よく観せて何になる。全てを無に して臨む心身の鍛練以外に何があろう。その修練の毎日をむしろ楽しみながら功まず、たゆまず精進し、自然に至れば美は自ずから成る。能の求めている真の美 しさはそこから生まれると信じていた父。父の求め歩んだ道は真の能へ通じているに違いない。私も父を信じ、その道を歩む。その先に真の幽玄の世界があるの ではなかろうかと。